|
しかし、真のベテランはいる、というのだ。
ここで次なる疑問が生じる。
はたしてこのロングオーダーはJapan specificなものか、はたまたWorld wide(global)なものか。
そういう視点で見るといろいろと思い当たることがある。
幕末にアメリカ視察を命じられた勝海舟は、老中から「かの国はどのようであったか?」と聞かれ、
「アメリカでは、政府でも民間でも、上に立つものほど、賢く怜悧で、わが国とは逆でございます。」と答え、
老中から「無礼者」と怒られている。
また、第二次世界大戦における日本軍の組織論として河合隼雄は次のように述べている。
「原為一少将や田中頼三少将など米軍の戦史に激賞されている即興能力の持ち主は後に左遷されていないまでも昇進していない。よきリーダーとなりうる日本人もいるが彼らは 「出世」はできないのである。つまり日本の組織の上層部はリーダーとして活躍する素質のある者を排除する傾向をもっている。」
また東京大学大学院経済学研究科の藤本隆宏氏は、次のように述べている。
「リーダーの方針が定まらず、意思決定者は会議の空気を読みあい、論理ではなく空気でものを決め、後手後手に回り、そして失敗する。幕末の幕府、戦前・戦中の軍部バブル崩壊後の政府や金融界などがそうであったと言えよう。要するに「強い現場」と「弱い本部」は日本の組織のひとつの伝統的特徴である。」
とはいえ、ロングオーダーという現象自体は、World Wideなものと思われる。
論語の為政第二に「直(ただし)きを挙げて諸(こ)れを枉(まが)れるに錯(お)けば則ち民服す。枉れるを挙げて諸れを直きに錯けば則ち民服ぜず。」 とあるが、これはたぶんとりもなおさずロングオーダーのことを言っている。
また、Steve Jobsは次のような事を言っている。
「会議や出世競争の世界では、経理とか事業管理部とかいった文科系のヤツラが必ず勝つのさ。そうして製品はクズとなり、品質は地に落ちる。」
これもロングオーダーに至るWorld Wideなメカニズムの一つであろう。
ロングオーダーに至るメカニズムにはWorld Wideなものもいっぱいあるが、Japanspecificなものもあり、それがかなり致命的になってきている、というのが筆者の視点である。
それがまさに、以前LMJでも議論になった「日本的モラリズム」ではないだろうか。
詳細は右記(http://www.lmj-japan.co.jp/blog/2013/02/20130118.html)に譲るが、
「自由と民主主義」に対する対抗概念として「日本的モラリズム」はある。
「日本的モラリズム」は「同質性」と「共通モラルの絶対性」を基礎としており「人々はみんな一緒」ということを前提とし、Sameを好むのに対し、「自由と民主主義」は、「人々はバラバラであって当然であり、絶対的な善意、正義価値は存在しない」という『価値的相対主義』を前提として、Differentを好む (アップルの「Think different!」もその方向の思想)
この「日本的モラリズム」は、経済学者で自由主義者のハイエクが、最も嫌った「全体主義:隷属への道」そのものではないかと個人的には考えている。

有名なタイタニックジョークには下記のようにある。
タイタニックの悲劇は乗員、乗客の数と救命ボ―トの数との不一致から起こった。
およそ半数の人間しか乗れなかった。まずは女子供からボ―トに乗り込む。
大半の男達は極寒の海へ飛び込まざるを得ない。
さて問題はここからだ。死にたくないのは男でも同じだ。その男達をどうやって説得したかだ。
英国人にはこう言ったそうだ。
「あなたはジェントルマンですね」そうすると英国人は黙って海に飛び込んだ。
米国人にはこう言った。
「あなたはヒ―ロ―になれます」すると米国人は「そうだ、俺がヒ―ロ―だ」と言って海に飛び込んだ。
ドイツ人にはこう言った。
「それがル―ルです」ドイツ人はル―ルに従って海に飛び込んだ。
さて日本人には何と言って説得したのだろうか。この答えが情けない。
「みなさん、そうしていらっしゃいます。」当たっているだけに涙が出る。然もこのジョ―クの作者は外国人というから、情けなさも限度を超える。それにしても、なぜ日本人は、人と同じであることに安堵を覚え、一人で新たな行動を起こすことができないのだろうか。
「理由は簡単です。答えはDNAにある」ソフトバンクの孫正義の回答である。
では何故、この日本的モラリズムがロングオーダーを生むか?
次回へと続く・・・
|
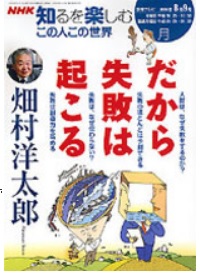 放送され、その第6週に「みずほ銀行統合失敗の事例」が取り上げられた。
放送され、その第6週に「みずほ銀行統合失敗の事例」が取り上げられた。


タイタニックのジョークは、読み終わって、胸に迫るものがありました。
英国、米国、ドイツに日本人を入れていただいて光栄です。
このジョークを、たとえば、英国人に語る場合は
英国人にはこう言ったそうだ。
「あなたはジェントルマンですね」そうすると英国人は黙って海に飛び込んだ。
ここのところで、英国人は、同じように胸に迫るものを感じるのでしょう。
最近の若い日本人に、このジョークが、我々のように説得力を持つかどうかは、定かではないと思います。
日本的モラリズムにはいいところももちろんあります。
私はテニスが趣味ですが、地主の人にテニスコートをつくってもらいたい時、相手が中国人やアメリカ人ならこう言うでしょう。
「この土地をテニスコートにすれば儲かりますよ。」
しかし相手が日本人なら次のように言うでしょう。
「この土地をテニスコートにすれば、みなさん喜ばれますよ。」